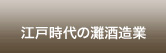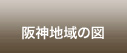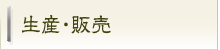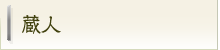番付は17世紀中期頃から、歌舞伎・人形浄瑠璃・相撲などの興業に伴い盛んに作成された。さらにこれらを模倣した種々の見立番付が流行したのだが、この史料はその中の江戸積酒屋の見立番付である。東の大関は伊丹(現・兵庫県伊丹市)の坂上(津国屋)の「剣菱」、西の大関は同じく伊丹の山本(木綿屋)の「老松」となっている。伊丹・池田(大阪府池田市)・西宮(兵庫県西宮市)が上位を占め、灘は前頭の下位に位置づけられている。
元禄期頃(17世紀後期)までは銘酒と言えば伊丹の諸白と呼ばれる濁酒であり、灘の清酒が台頭してくるのは18世紀前期であり、またそれが飛躍的に生産量を上げるのは19世紀初頭のことである。この番付で伊丹や池田に比して灘が下位に位置づけられているのは、この史料が灘酒造業が発展する以前の17世紀後期~18世紀前期頃の作であったためであると考えられる。