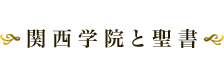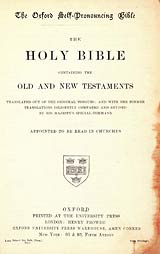ホーム > 関西学院ゆかりの聖書 > 関西学院初代院長W.R.ランバス所蔵の聖書
関西学院初代院長W.R.ランバス所蔵の聖書[聖書の一部を掲載]
| 書名 | The Holy Bible, containing the Old and New Testaments |
|---|---|
| 出版地 | London ; New York |
| 出版者 | Oxford University Press |
| 出版年 | [1902?] |
| 所蔵場所 | 学院史編纂室 |
1998年9月28日の学院創立記念日の式典で、創立者 W.R.ランバス監督が愛用した聖書の受納式が行われた。贈り主はランバス先生の令妹ノラさんの孫に当たるフロリダ州在住のオリーブ・シェレツ・ランハム夫人である。この聖書はもとミシシッピー州マジソンのパール・リバー・メソヂスト教会(ランバス一家の母教会)の説教台に置かれていたもので、後に州都ジャクソンにあるミルサップス大学(メソジスト系)のランバス・ルームに移され、大切に保管されていたが、それをランハム夫人が関西学院に贈りたいとして、J・B・ケイン牧師から譲り受け、ディラード大学の藤田允先生(元学院国際センター・ディレクター)を介して宮田満雄前院長が訪米の際に預かり携えて下さった。革表紙にWALTER RUSSELL LAMBUTHの金文字が印されているが、むろんランバス愛用の聖書だから特別に値打ちがあると言うのではない。印刷されたブックという意味では私たちの聖書と何ら変わりないからである。しかし、ランバス先生がこの聖書をどう読んだか、先生が愛用のバイブルから読み取ったメッセージは何であったかを知ることは大事であると思う。100年近く前の書物であるから、持ち上げると手に皮の粉がつくような時代物だが、そっと頁を繰っていくと所々にアンダーラインや丸印がつけられているのが目に入った。新約のガラテヤ5章1-6節がその一つである。この聖書テキストのテーマは「自由と愛」、そして「と」で繋がれた両者の関係が深いところから問われている。「自由」とは、通常さまざまな拘束からの解放を意味している。人間には誰でも義務やルール、あるいは他人や社会からも自由になりたいという欲求がある。しかしそういう「~からの自由」はついに気まぐれな野放しの自由にずり落ち、時として破壊的にも作用する。しかし、ここでの使徒パウロの証言は、そのような消極的な「~からの」逃避の自由ではなく、むしろ積極的な「~への」決断の自由、すなわち他者や社会にかかわることへの自由、それが本当の「隣人愛」と「奉仕」に他ならないという提唱である。
ガラテヤ5章1-6節のテキストが、宗教改革者マルティン・ルターの有名な『キリスト者の自由』(岩波文庫)冒頭に掲げられた二つの命題の典拠であることはよく知られているが、私たちはまたこの聖書のメッセージが関西学院のスクール・モットー"Mastery for Service"の精神と深く響き合うことに改めて気づかされる。〈マスタリー〉とはすなわち実力をつけ自由を獲得することの謂れである。しかしその「自由」を奉仕という「愛」への意志的な自由として活かして用いること(ガラテヤ5章13節も参照)、それが真の意味における〈サーヴィス〉であり、〈フォア〉という目的を指示する前置詞で不可分に結びついたMasteryとServiceの正しい関係、学院教育が目指すゴールであることがよく分かる。今、高等部の玄関ロビーの正面に野中浩俊先生揮毫による聖句「すべての人の僕たれ」(マルコ9章35節)という立派な書が掲げられている。普通に考えると、「主人」と「僕」というのは正反対のイメージである。にも拘わらず、Servantこそ実は本当のMasterなのだという謎のような逆説がこのように堂々とスクール・モットーで謳われること自体、今の時代の私たちには何か不思議にさえ思われる。しかし、私はランバス先生が愛読した聖書のこの箇所で、特に「キリスト」の一語にアンダーラインが付されていることに注意を惹かれ、ここに謎を解く鍵があることを知った。ランバス先生は、イエス・キリストこそ、すべてを与えたすえ十字架にかけられ、真の〈サーヴァント〉となった本当の〈マスター〉であったことを心から信じ、そのイエス・キリストに従って、世界万人に仕える献身の生涯を生き抜かれた。アメリカ人である宣教師が、日本人のために建てた関西学院はその生きた証しである。
(名誉教授 山内一郎)